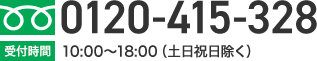運動と自律神経の専門家・ふみ先生がお届けする「健幸ライフのすすめ」
テーマ:健幸ライフへの自動運転!「自律神経」を整える3つのポイント
寝ても疲れがとれない、元気が出ない、冷えやむくみがひどい、長年の肩こり腰痛もち、イライラしやすい…そんな悩みがあれば、「自律神経の乱れ」が原因かもしれません。
「自律神経」は全身の臓器や血管を支配し、呼吸や循環、消化、排泄といった、あらゆる生理機能を調節。24時間365日休むことなく、心身の健やかなはたらきを支えています。
さらに、自律神経は2つの種類―「交感神経」と「副交感神経」―あり、それぞれカラダの組織に対して相反する役割を果たしています。「交感神経」が優位になれば心拍数や血圧が上昇し、筋肉が緊張するなど、活動モードへ。一方、「副交感神経」が優位になれば、胃腸がよくはたらき、休息と回復が進められます。この両者がバランスよくはたらくことが、「健幸ライフ」の要です。

ただ、自律神経がなせる「活動の量(トータルパワー)」には限度があります。トータルパワーは10代をピークとして加齢とともに低下し、40代以降ではその半分にまでダウン。そこで日々の「自律神経のメンテナンス」が不可欠なのです。
【自律神経メンテナンス「3つのポイント」】
①「体内時計」のリズムに沿って生活する
自律神経は「体内時計」とリンクして動き、さまざまなホルモン分泌や臓器のはたらきと関わっています。そのため不規則な生活によって体内時計が乱れると、自律神経のはたらきも崩れることに。
体内時計のリズムをつくるのは、「日光」と「朝ごはん」です。朝一番に太陽の光をあびれば脳内で「セロトニン」の分泌が高まり、交感神経にスイッチオン。頭がシャキッとし、一日を清々しくスタートできます。
②「腸内環境」を整える

「腸」は自律神経などを介して「脳」と連絡をとりあっています。“緊張や不安を感じるとお腹をこわす”、という現象もまさにそれ。腸内環境は「腸内細菌」のバランスによって決まります。乳酸菌やビフィズス菌といった「善玉菌」をふくむ「発酵食品」を食べる、腸内細菌のエサになる「食物繊維」を積極的に食べるなどが、腸内環境を整えるのに有効です。
③質のよい「睡眠」をとる
自律神経をメンテナンスする一丁目一番地は、「睡眠」。日中、優勢になっていた「交感神経」から、夕方以降は「副交感神経」へと切り換わり、脳やカラダの休息と回復が進みます。快眠のためには、「寝る前にスマホを見ない」、「夕食は寝る2時間前までに済ませる」、「湯船につかって温まる」などを心がけましょう。ストレッチや軽めのウォーキングも筋肉の緊張をやわらげ、スムーズな寝つきにつながりますよ。
「自律神経」は、私たちが元気や若々しさを保つのに大きく貢献しています。ぜひ、ふだんの生活で「自律神経」をメンテナンスしていただき、充実した毎日をお過ごしください。